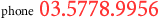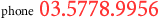update:2016.09.26
検察官が公判資料紛失 名古屋地検支部、処分検討 共同通信
名古屋地検は9日、管内の支部に勤務する検察官が5月、被告名が記された過去の公判の冒頭陳述や論告の要旨など約40の文書を保存した私物のUSBメモリーを紛失したと発表した。
地検によると、検察官が2005~07年にほかの地検に勤務し、公判担当だった当時の文書で、被告名以外の個人情報は記されていない。法務省の内規は「要保護情報」を庁舎外に持ち出すことを禁じており、上級庁と協議し処分を検討している。
検察官は5月下旬、公判を終えて裁判所から庁舎に戻った際、USBメモリーが入ったバッグを裁判所敷地内に置き忘れたことに気付いた。すぐに戻ったが、既になくなっていたという。
玉岡尚志次席検事は「個人情報が外部に流出しかねない事態を招き遺憾。指導を徹底する」と話した。
引用ここまで。

個人情報の紛失事件は、あとを絶たない。多くは書類であるが、電子化が進んでいるのでデータを含んだUSBの紛失というケースもある。税関の職員が通勤中に個人情報を含んだUSBをなくしているという事件もあった。
USBメモリは人差し指くらいの大きさしかないので紛失しやすいメディアだ。
USBメモリを業務で利用するとなると、機密性のレベルの違いがあっても個人情報がどうしても含まれてしまう。だから、多くの企業では、USBを利用した日常的な情報の移送を禁止している。
しかし、オフィスを出て、外出先で文書を作成したり受け取ることがある場合には、業務効率から、禁止されていると分かっていても利用してしまうケースがある。
今回のケースでは、公判記録となっている、裁判で利用される情報であるので一般に流出することはプライバシー侵害で、第三者がそれを具体的に悪用したかどうかの事実がなくても、被害者に精神的苦痛は想像に難くない。
データの質として重たいものを利用している認識を持つ必要がある。
スパイ映画ではないが、もしもUSBを落とすことが、自分の人生に影響を与えることを分かっていたらかばんではなく身に着けていたかもしれない。
後悔は先にたたない。禁止されていることを注意深く実施することが薦められることではないので、従業者を管理する管理者は、禁止するだけでなく安全な利用方法も提供し、万一の際には従業者の「規則違反」とならないようにしてあげるべきだ。
具体的な取り組みとして、クラウド環境の活用で、デバイスは必要な際にアクセスするだけで移送時にはデータを管理用のサーバにあげるという方法もある。
紙媒体の場合には、仮想空間に保存は無理なので、扱う情報を分割して流出の際の被害を少なくするという方法をとっている企業もある。
従業者は、自分の身を守るための個人情報保護をお勧めしたい。
<PR>個人情報保護をしたくなる、業務に実践しやすくなるステックワイアードのCPA資格講習、好評です。